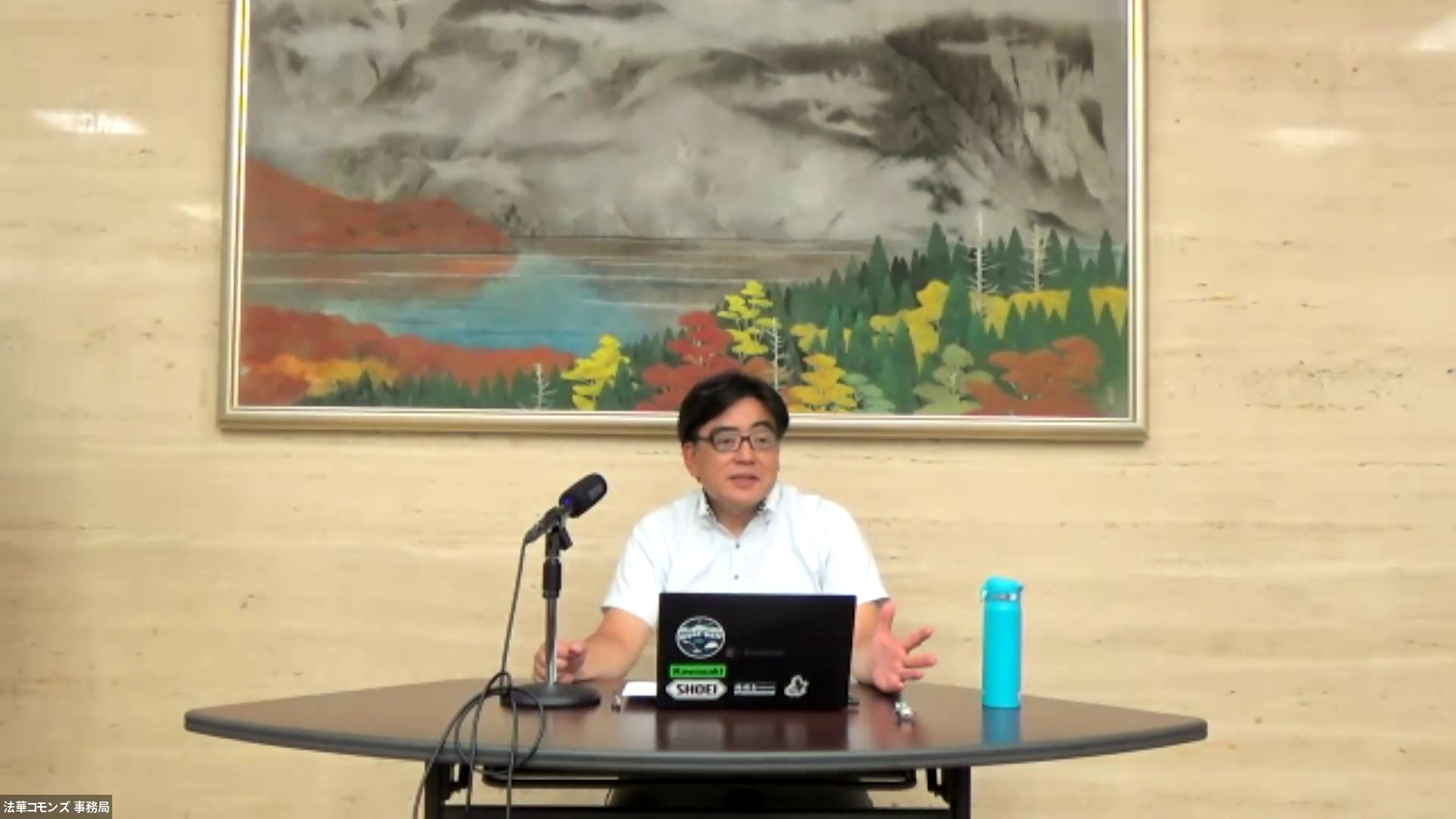令和7年7月22日(火)18時30分~、菊地大樹先生による2025年度前期【歴史から考える日本仏教⑫】〈中世社会と寺社の諸相〉の 第4講「寺社聖教の発展と流布」が執り行われた。今回は、全4講の最終講となることから、新宿•常圓寺様祖師堂地階ホールを会場とし、対面&オンライン実況の形式で開催した。
菊地先生は、初めに、古文書•古記録•典籍という文献史料の内、典籍の分類に収まる「聖教」は、更に「経典」「教理書」「儀軌」に分類されることを示され、その上で、聖教史料調査の歴史、近年の研究の傾向、更には、中世寺院の様相について詳しく論じられた。論中、日蓮教団を含む中世仏教教団では「聖教」が師資相承の核と位置付けられたことを指摘され、その意義を再認識した聴講者が多かったことと思う。
次いで、先生は、延暦寺•青蓮院門跡の事例を皮切りに、東寺文書•仁和寺文書•高野山文書、また、南都寺院の聖教について、その詳細に触れながら、寺院組織と史料群の関わりの特徴をご教示くださった。
以上を承け、菊地先生は以下のように纏められた。
•仏教典籍の根底には経律論の「三蔵」があるが、とくに経論については、注釈がまた
注釈を生み、ときには注釈が中国・日本撰述経典(いわゆる偽経・疑経)を捜索する
という複合性においてみていかなければならないこと。
こうして何代にもわたって蓄積された寺院経蔵の中には、中世の大寺院内部に成立
した院家と法流にもとづき、以下のような階層性がある。
① 大蔵経にも収められているような基本的な経典類(ただしそれらに法流独自の読み点や注記が付されていく場合もある)。
② 経典から生まれた権威ある注釈書(たとえば天台三大部、唯識論、大日経疏・義釈など)。
③ ①②から随時作成され、師資相承により法流の核となる聖教群。
•また、聖教は、寺院における日常的な実践活動の所産でありら教学に関わる者だけではなく、宗教施設を維持していくために作成・蓄積・保管されていったすべての文献資料を「聖教」として見直してみることも必要であること。
ー今後の日本仏教研究全体に重要な視点を供する、菊地先生ならではの貴重な御講義であった。(スタッフ)