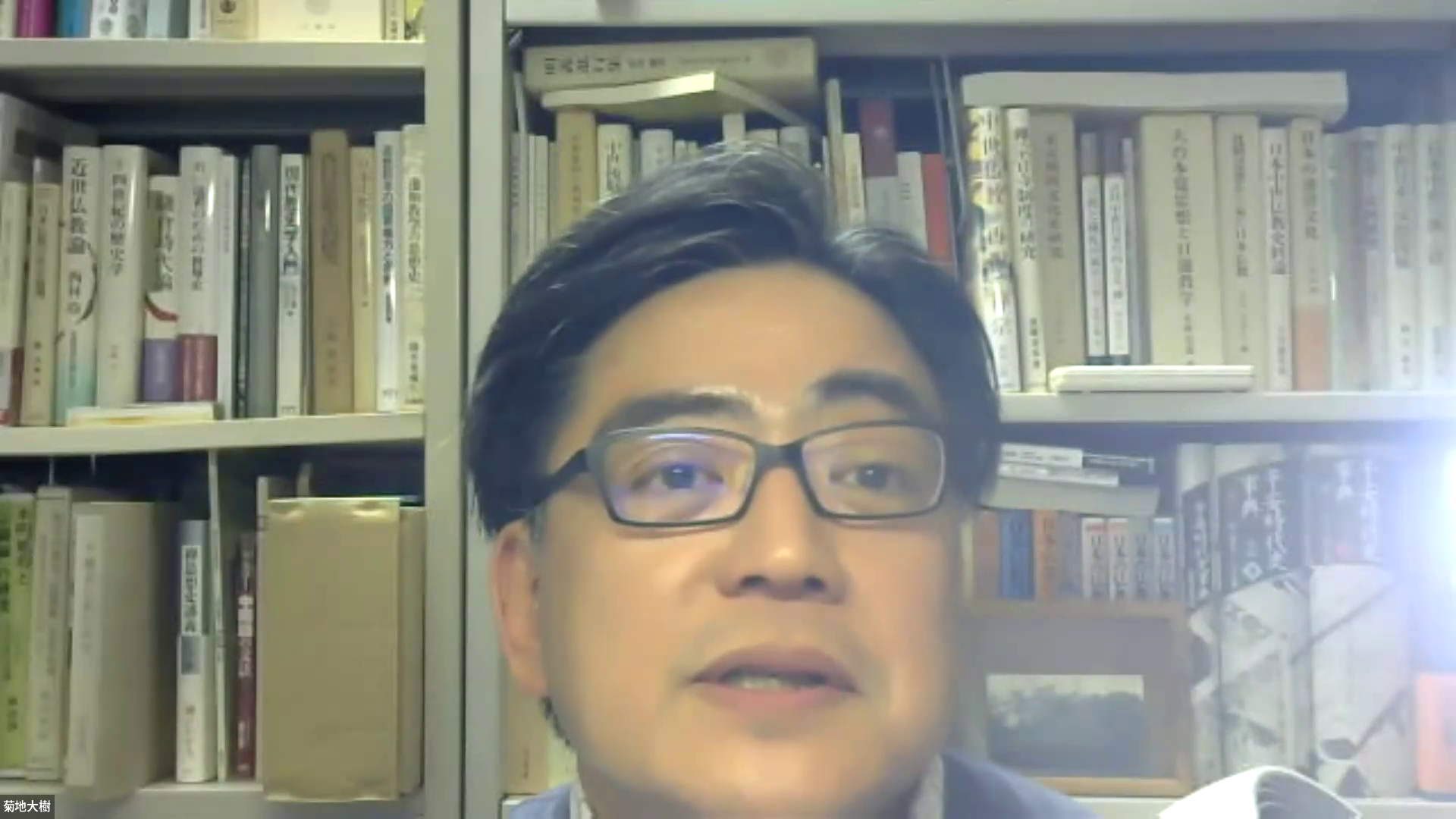令和7年6月17日(火曜)午後18時30分~、菊地大樹先生による連続講座「歴史から考える日本仏教⑫中世社会と寺社の諸相」の第3講「僧尼のライフサイクルと身分」が、オンライン配信により行われました。
第3講となる今回は、出家をして僧や尼となった人々の社会階梯、つまり社会のなかで僧尼がどのような階級・立場であったのか、またそれにまつわる僧尼の暮らしがどのようなものであったのか、などについて詳細な解説をしていただきました。以下、講義の要点を記します。
日本では、西暦584年に出家した女性が最初の出家者であるといわれています。その後崇仏派の曽我氏の外護や聖徳太子の仏教保護政策によって、僧尼の数は次第に増えていきました。そうした僧尼の増加にともない、僧尼を統制するための制度が整えられていき、僧尼のランクと昇進コースが形成されていきます。平安中期以降になると親王などの高貴な身分の人のために、「閑道昇進」と呼ばれる裏口入学のような出家制度も作られたそうです。
次に、慈円、親鸞をはじめ、天皇家や貴族から出家した僧尼など、上位・中位・下位の身分の違いとそれぞれの出世に至る個別の背景について、多くの資料をもとに解説していただきました。また、日蓮聖人の出自については、遺文のなかで日蓮聖人自身が語られることが少ないため、いまだに不明な部分が多く残っています。菊地先生は、上述した出世僧のさまざまなケースを踏まえたうえで、日蓮聖人の出自と出家の動機について、独自の見解を開陳してくださいました。なお、ここではその詳細は述べませんので、興味のある方はぜひご受講ください。(スタッフ)