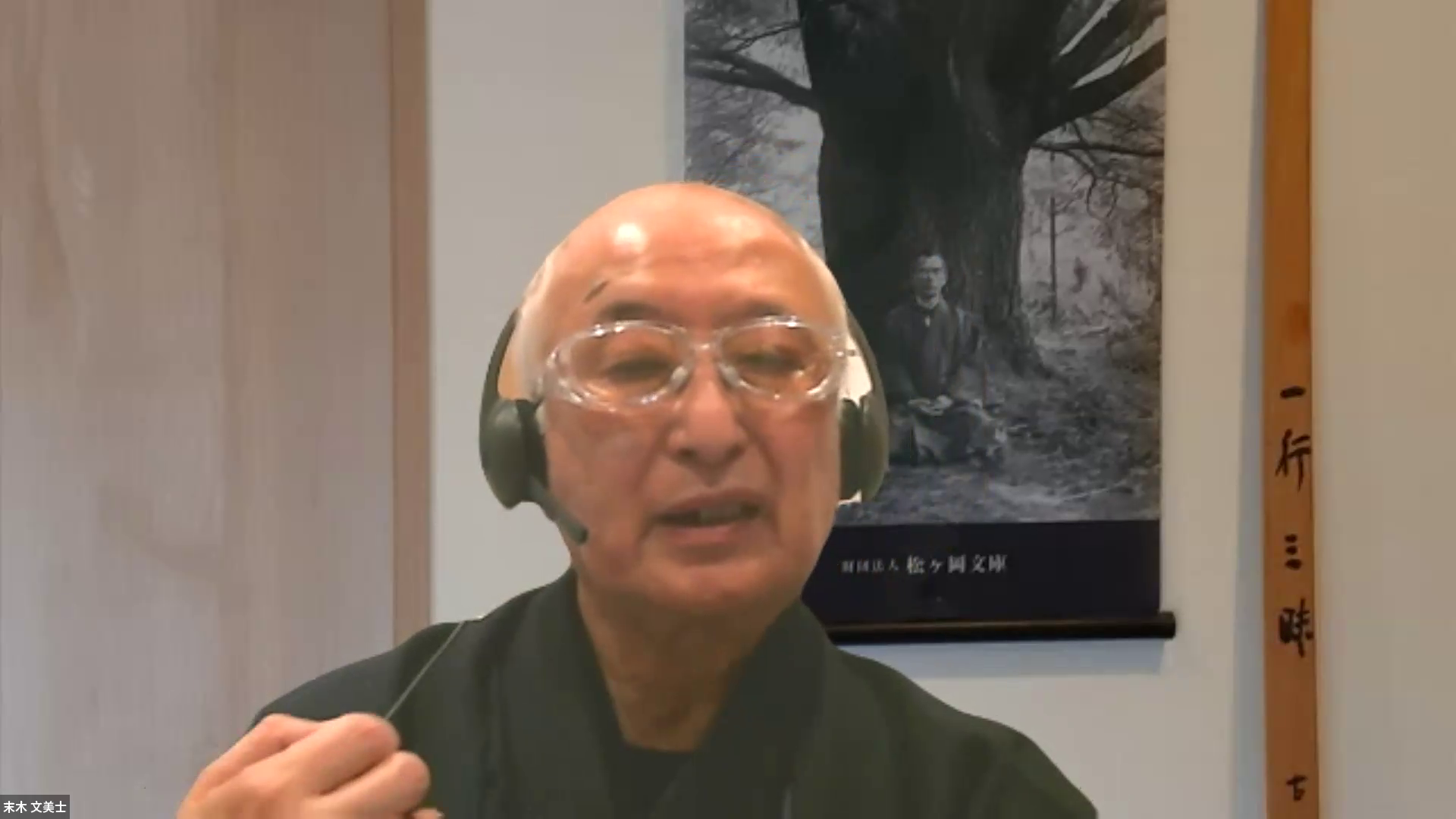令和7年4月9日(水)、末木文美士先生による講座「仏教哲学再考②−『大乗起信論』を手掛かりにⅣ−」の第13回目が開催された。今回の講義は、『大乗起信論』(以下『起信論』)と『釈摩訶衍論』(以下『釈論』)の思想が、近代に至るまでの日本仏教に与えた影響を検討する内容であった。
はじめに、『起信論』から法蔵(随縁・不変真如)へ、そこから澄観(華厳)・湛然(天台)・『釈論』への展開を再確認した。そして、近世の鳳潭が従来の起信論理解(法蔵)への原点回帰を主張したことで、近代の『起信論』重視(原坦山、村上専精、鈴木大拙等)へと繋がっていくのではないか、と述べられた。さらに、思想内容の見通しとして、先生は「日本では『起信論』で説かれるような如来蔵をあまり重視せず、『涅槃経』の仏性説が前提となっていく」ことを指摘された。
続けて、仏性説については、「最澄と徳一の三一論争、良源と仲算の応和の宗論以降は議論されず、それ自体問題化されることが少なくなる。そして、可能性(如来蔵的)としての仏性よりも、すでに実現しているとする真如論へと発展していく」ことを明らかにされた。また、如来蔵批判については、「日本仏教は基体説として認められるが、如来蔵縁起ではなく真如縁起である。日本ではインドの中観と唯識を権大乗に位置付け、その上に実大乗としての理論を展開しているため、インド仏教の理論と日本仏教の理論は根本的に性格が違う」と詳説された。
次に、末木著『近世思想と仏教』(法蔵館、2023)を参考に、近世初期の不干斎バビアン『妙貞問答』、林羅山と松永貞徳の『儒仏問答』、鈴木正三『因果物語』、近世中期の増穂残口『神路之手引草』『神国増穂草』『艶道通鑑』、新井白石『鬼神論』、近世後期の服部中庸『三大考』、平田篤胤『鬼神新論』『霊能真柱』、六人部是香『顕幽順考論』を取り上げ、近世における三世両重の因果説(仏教)と来世否定論(儒教)について解説された。
最後に、近代で霊魂論が問題になった原因について、末木著『霊性の日本思想』(岩波書店、2024)を参考に、加藤弘之・清沢満之の三世因果論争(『哲学雑誌』)、清沢満之『宗教哲学骸骨』、井上円了『霊魂不滅論』、南方熊楠と土宜法龍の往復書簡、高橋五郎『霊魂実在論』、妻木直良『霊魂論』を取り上げ、キリスト教の霊魂不滅論と唯物論の霊魂否定論に対する仏教側(本来仏教は霊魂という言葉を使用しない不利な状況)の解釈を示され、講義終了となった。
次回からは空海、安然といった日本仏教に焦点をあてた講義となります。末木先生の最先端な知識を拝聴できる貴重な機会になることは確実です。先生は聴講者に対し、分かりやすく解説して下さいます。新規聴講も問題ありません。皆様の聴講申し込みをお待ちしております。なお、本講座はリモート開催となっており、講義動画も受講者に配信し、期間内であれば何度でも見ることが可能です。詳細につきましては、「法華コモンズ」ホームページからご確認ください。(スタッフ)