大竹晋先生の特別集中講座「読経に意味はあるか――読経の歴史、読経の理論、読経の将来」の第1回講義が、10月4日(土)午後1時半より新宿常円寺祖師堂地階ホールにて開講された。興味深いテーマのためか、受講者は会場のほかにオンラインで14人参加の講義となった。
まず大竹先生は読経の意味付けを自己の為と他者の為に分け、自己は暗記だが、他者の為では①生者のための講経と②亡者のための慰霊に分けた。特に慰霊の読経については、その典拠を『大唐西域記』と『梵網経』から挙げて、日本の諸宗で亡者のために各宗所依の経典が音読されるようになるのは『梵網経』の代わりだったのではと推測された。
また、日本での読経は「漢文の棒読み」が基本になるが、近代に入り読書が黙読となり漢文の読解力が衰えて経典解釈の講経も消滅すると、漢文棒読みでは檀信徒が理解不能のため、長時間の読経に苦痛を訴えるようになったという。この苦痛をどうするかが問題となり、明治期にさまざまな読経の理論が発表された。今回の講義では大竹先生がその幾つかの論考を引いて、それを読み上げながら詳しく解説された。
なお「講説(経典の講義)」については、男僧の場合は中国の魏の朱士行が甘露5年に『道行般若経』(西暦260年)を講義したのが最初で、尼僧の場合は東晋の竺道馨が『小品般若経』を講義したのが最初だが、天台大師は常に講経を欠かさなかったため著作として残ったという。しかし講経は日本近現代には消滅して、代わって仏教の出版文化が隆盛したと説明があった。
さて、講義で引用された論考は下記の3つとなる。
〇高田道見「読経改革論」(明治四十年): 訓読による読経を主張。
〇清水友次郎「読経廃止論」(明治四十二年): 読経の廃止を主張。
〇梅原隴圃「読経は廃止すべきか」(明治四十二年): 読経の廃止反対を主張。
まず髙田道見の「読経改革論」の論旨だが、明治の社会革命は諸寺院にも大きな影響を及ぼしたが、いま仏教の社会的意義は葬祭の一点にあり、住職の実務は読経回向の葬祭事業で、七万の寺院十万の僧侶・家族の経済はすべて読経回向料の檀施による、と断ずる。そして、社会百般の現状は悉く改革されつつある中で、「仏教各宗派は依然として此の葬祭法を革新せざるは何ぞや」と嘆き、「其の革新とは従前の棒読を廃して悉く訓読と為すにあり」と読経の訓読を提唱、また「白骨の御文」など各宗祖の和文や経典の和訳をあげて、「古昔は分からぬを以て稀有なりと思い~今は善く分かるを以て有難しと感ずるなり」として、現代にも通ずるよくわかる仏教の必要を説いて終えている。
次の清水友次郎の「読経廃止論」は、「読経、々々、アゝ何たる奇習ぞ」で始まるように、読経を「進歩改革に志ある仏教家の須らく第一着に廃止すべき大悪習慣」として、「読経の無益有害なることは~火を見るよりも明らか」「仏教はすでに生命を失っている」「(儀式を主とする)旧仏教は、~その悪習慣と共に一日も早く消滅し去るが、我々のため、国家の為、世界の為」と極めて手厳しい。しかしこの極論が、自身の父の病死に際して全ての仏事を担った苦い体験からも来ることが最後に明かされる。そして論考末に新仏教運動の高島米峰の寸評が続き、「清水兄のこの論、父の喪といふ、非常時の場合に際しての、実験の声である。旧仏教の徒、須くまづ、深厚の敬意を表して精読せよ」とあって、執筆時の状況説明にもなっている。
この清水論考に対して梅原隴圃が反論したのが「読経は廃止すべきか」(上下)である。梅原は、清水を「潜かに敬慕している」「率直に疑いを打ち明けて御高説を仰ぐ」と遠慮がちだが、(上)では清水の「絶対廃止」の論拠が弱く、漢訳の棒読みが苦痛などは改良説に属するもので、また読経作法が原始的な言語崇拝によるとしても、読経功徳の思想が素朴な原始的信念だとはいえないとして、経典の思想的価値にも言及している。また(下)では信念を持って宗教的生活を味わう人にとっては「読経は宗教的情操の上に深き感銘を与ふる」価値があるとして、仏教界の読経の弊害は改革すべきもので「清水氏の絶対読経廃止論に対しては角を矯めんがために牛を殺すやうな感じしてならない」と述べて終えている。
以上の三論考を詳しく解説された後、『新仏教』紙や『中外日報』紙に掲載されたこの読経改革・廃止論議のその後の経過を説明して、講義は終了した。その後の質疑応答では、引用された読経廃止論に反論する意見が出るなど、会場またオンラインともに質疑が盛り上がり、予定を30分超えて午後6時に終了となった。
今回の明治期の三論考は近代化路線が強い内容だったが、次回の第2回講義で取り上げる関連論考は、鈴木大拙「読経の神秘」(大正15年)や中山理々「僧侶読経論」(昭和17年)などで、より読経の意味を掘り下げる内容が予想される。次回は11月8日(土)、同じく午後1時半~5時半の開講、ぜひ受講申込をお願いします。 (担当スタッフ)
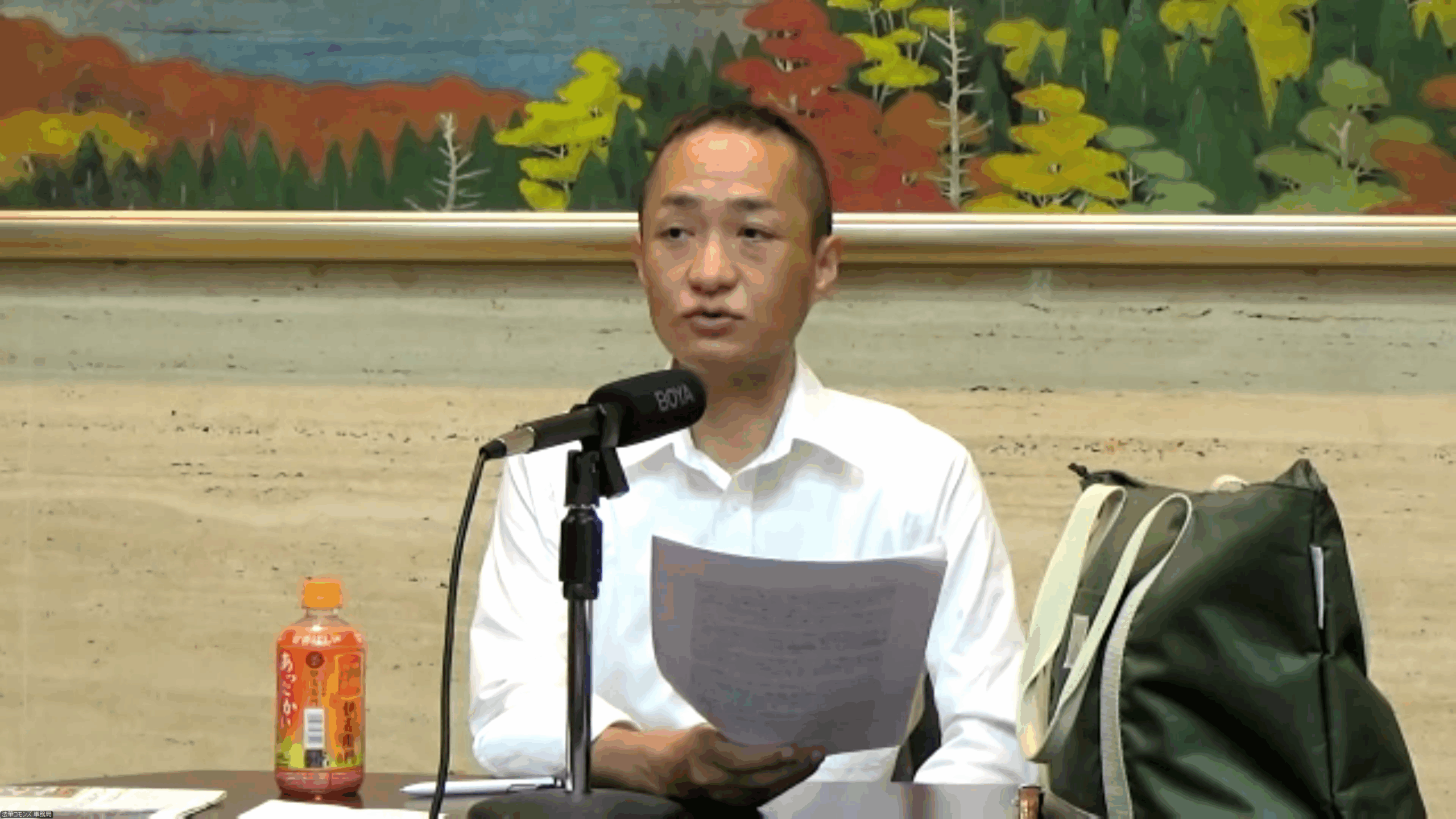
© 2025 法華コモンズ.