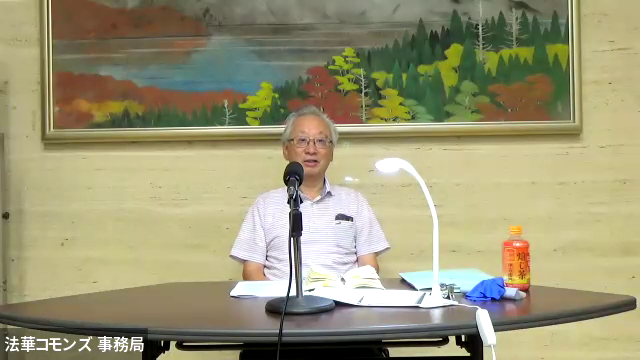9月29日(月)午後6時半より常円寺祖師堂地階ホールにて、前期の最終回となる菅野博史先生「『法華経』『法華文句』講義」(通算88回目)が開講されました。
今回からテキストの『法華文句(Ⅲ)』は、「薬草喩品を釈す」(790頁)に入りました。経文では、「信解品」の最後で摩訶迦葉が釈尊の説法を「一乗の道に於いて宜しきに随って三と説きたもう」と述べたことを受け、世尊が自らの説法を「一相一味の雨が大中小の草木を等しく潤し成長させる」ようすに喩えるところから始まります。そして『文句』の解説では、「独り薬草を以て名を標するは~」と始り、まず薬草の意味を四悉檀の解釈から見ていきます。
題名に「薬草」を高く掲げる理由として、土地があり雨があり草木(薬草)がある中でそれぞれ有用だが、薬草はとりわけ有用なので、仏の譬喩と教えを深く領解した四大弟子(声聞)を薬草にたとえて「薬草喩Ă品」と呼ぶ、と述べます。これを四悉檀での解釈で「世界悉檀」として、次に薬草(草木)が雨(仏乗)を受けて徐々に成長して人を救う姿を声聞に重ねて「為人悉檀」とします。また薬草の働きは病を治す薬王であり、やがて身を変じて仏智見を開くに至ると述べ、それを授記された声聞のすがたに重ねて、それを「第一義悉檀」と「対治悉檀」として解釈しています。
こうした四悉檀による解釈もふまえて、科文の「正しく開三顕一を叙す」では、「一切法」とは「七方便」である、と述べます。「七方便」は、天台教学で円教を聞くまでの立場をいい、「人・天・声聞・縁覚と、蔵通別の三種の菩薩」の七段階です。人天の為には五戒・十善を説き、二乗の為には四諦十二因縁、三蔵の為には藏教の六波羅蜜、通教の為には空、別教の為には次第を説いて、如来蔵を開いていく段階とします。「これをその開三を領するを述すと名づくるなり」(797頁)と述べたところまでで、今回の講義を終了しました。
しかし今回最も驚き印象に残ったのは、質疑の後に菅野先生が補足説明された「薬草喩Ă」の解釈についてでした。実は「薬草喩Ă品」のサンスクリット本には、三草二木の喩えの他に、あと二つの喩えが出て来るとのことで、一つは陶器(入れ物)の喩えが述べられていて、仏乗という陶器は一つだが、中に入れるもの(声聞・縁覚・菩薩)により陶器の性格が変わるという話。もう一つは盲人が薬草によって視力が回復するように仏は医王として衆生を目覚めさせるという喩えで、これが「薬草喩Ă」の元との話です。しかし鳩摩羅什の翻訳にはこの二つの譬喩が訳されていないので、羅什の訳した法華経には無かったのか、あるいは羅什が訳さなかったのかは分からずに、研究の対象にもなっているそうです。
次回の10月27日講義からはテキスト『文句(Ⅲ)』798頁からです。初めての方も充分について行ける講義ですので、ぜひご受講下さい。(担当スタッフ)