菅野博史先生「『法華経』『法華文句』講義」前期3回目が、6月30日(月)午後6時半より常円寺祖師堂地階ホールにて開催されました。
今回の経文の内容ですが、子に財産管理を託した長者は、子が一人前になった頃に死期を悟り、我が子への相続を告知すべく子に命じて親族・国王等を呼び集めて、皆の前で「この子は我が息子で、私を捨てて家を去り、五〇余年も捜し求めたが偶然に家に戻り全財産を管理している。この男は我が子であり、私は実の父だ」と述べるところまでです。
テキスト『文句(Ⅲ)』では767頁3行目「第二に「然其所止猶在本処」からで、子が完璧に全財産を管理しながらも、もとのあばら家に住んでいた、というところです。ここの『文句』の解釈は、子である二乗が羅漢の位のままで、自らを大乗の菩薩になれないと思い込み、未来に成仏すると思わないことを『維摩経』の生蘇味の教位として、次の全財産を管理する段階を般若の熟蘇味の教位としています。
また、財産管理を託すにあたって長者は子に「今、我は汝とすなわち為れ異ならざればなり」と語るのですが、子はなお劣心を捨てずにいます。しかし、漸くに全財産(大乗)に通暁して大心を起したことを見て、長者は「親族・国王・大臣・刹利(武士)・居士」を集めます。『文句』の解釈では、親族とは「十方の法身菩薩の影響(=影向)の者」たちで、仏の分身です。国王とは『法華経』を頂点とする「経王」のことで、全ての経王は『法華経』に会入します。また弥勒等の大菩薩が「大臣」、初地より九地までを「刹利」、三十心を「居士」とみて、全て釈尊の所化たちとします。また、実の父子であることを明かす「父子の結会」を大通智勝の因縁の如しと解釈して、子である衆生達は過去に結んだ大乗の教えに背いて、無明の闇の生死に逃れて(捨吾逃走)、六道輪廻を彷徨う(五十余年)のですが、「忽ちに此の間に於いて偶たま会いて之を得たり」の通り、はじめて今日、感と応の道が交わった(『文句』773頁末行)、というところで講義終了となりました。
次回の7/28(月)講義は、『文句(Ⅲ)』774頁1行目の「今我所有」の下は~」、科文で「正しく家業を付するを明かす」から始まります。初めての方もついて行ける講義ですので、ぜひご受講下さい。(担当スタッフ)
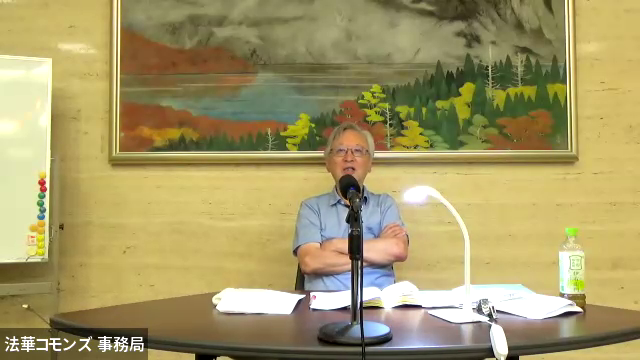
© 2026 法華コモンズ.